このページは、校報誌「キャッチボール」で紹介した教材・教具のダイジェスト版です。
どうぞご活用ください。なお、使い方やご不明な点は、本校までご連絡ください。
![]() 教材・教具について
教材・教具について
このページは、校報誌「キャッチボール」で紹介した教材・教具のダイジェスト版です。
どうぞご活用ください。なお、使い方やご不明な点は、本校までご連絡ください。
![]() 教材・教具リスト
教材・教具リスト
| 1 | 2 | 3 | 4 |
 |
 |
 |
 |
| 特殊はさみ | パラシュート | 会話補助装置(1,2) | スポーツ吹き矢 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
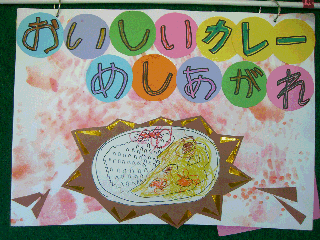 |
 |
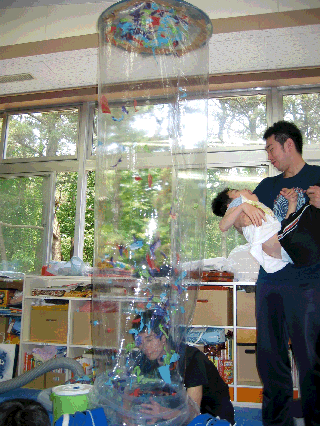 |
 |
| オリジナル創作絵本 | 筆記補助具① | お花紙タワー | フィンガーペインティング |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
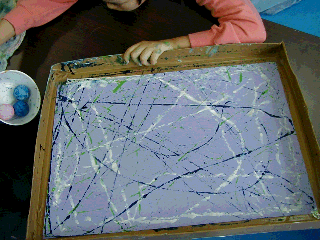 |
 |
 |
 |
| ころころアート | 机 | いす | 歩行器 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
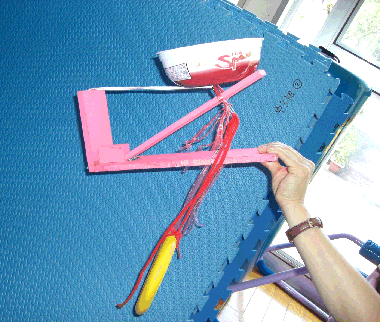 |
 |
 |
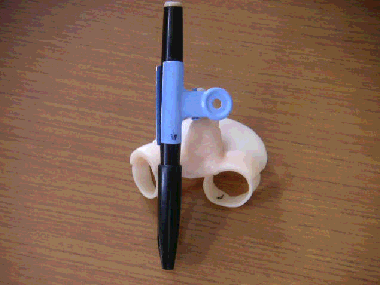 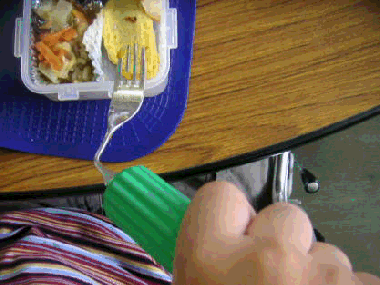 |
| 投球補助具① | 投球補助具② | キャスターボード | 筆記補助具② 食事補助具 |
| 17 | 18 | 19 | 20 |
 |
 |
 |
|
| ソリ君 | 楽器演奏補助具① | 楽器演奏補助具② | イルミネーションの部屋 |
| ☆ こんな子どもに・・・ | 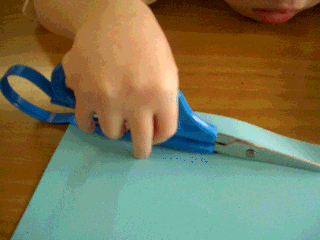 |
| 力の弱い児童生徒や開閉が困難な児童生徒に。自分で切ることができたという達成感を味わうことができます。 | |
| ☆ 使い方 | |
| 握って使う一般的な使い方の他に、柄の片側を机などの面に密着させ、もう片方の柄を上から押し上げて切り進める使い方もあります。 | |
| ☆ Let's try !! ☆ |  |
| 市販の粘土とはさみで、固定式のはさみを作ることができます。底には滑り止めマットを張り付けます。簡単にできますのでお試しください。 | |
| ☆ こんなはさみも・・・ ☆ | 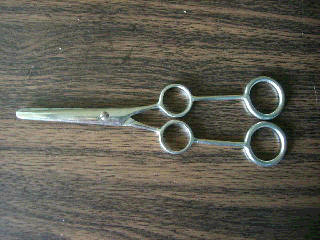 |
| はさみの使い方を学習するために、左のような形のはさみもあります。柄に近い方に子供の指を、遠い方に支援者の指を入れて使います。 |
|
| 指がカスタネットのような形になっています。スイッチと同様に弱い力でも切ることができます。 持っていてもおいていても使用でき、刃先もカバーがついているので安全です。(市販品です) |
 |
| ☆ こんな子どもに | 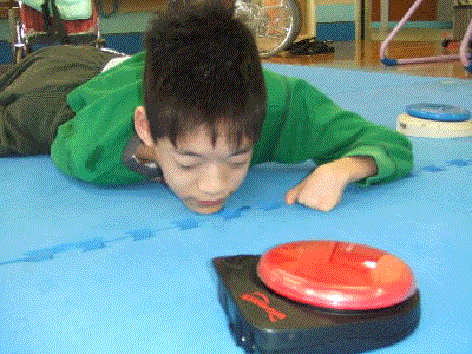 |
| ・ 発声が困難な児童生徒に。 あらかじめ録音した言葉を再生できるので、返事やあいさつをするときなどに利用できます。スイッチ部分が大きく、わずかな力で押すことができます。 |
|
| ☆ 使い方 | |
| 授業だけでなく、日常生活でも「おはようございます」などの言葉を録音しておき、車いすの押しやすい位置に固定すれば、いつでもあいさつができるようになります。 学習発表会などで台詞をいう時にも活用できます。 |
|
| ☆ Let's try !! ☆ | |
| スイッチを押すことが大好きな子どもには、少し離れたところにスイッチを設定し、探索活動や移動する力を引き出す手段として活用することも考えられます。 また、BDアダプターなどと接続することで、おもちゃやラジカセなどのスイッチにすることもできますので、用途が広がります。 |
|
3.会話補助装置(2)
| 「3会話補助装置」で取り上げたスイッチ活用の応用編です。ぜひお試し下さい。 | |
| ☆ さらに・・・ ☆ ACリレーという専用の部品を用いて市販の電化製品と接続すると、このスイッチ操作一つで電源のON,OFFが容易になります。扇風機などの電気製品に使用できます。ミキサー等につなぐことで、作業学習にも活用できます。 |
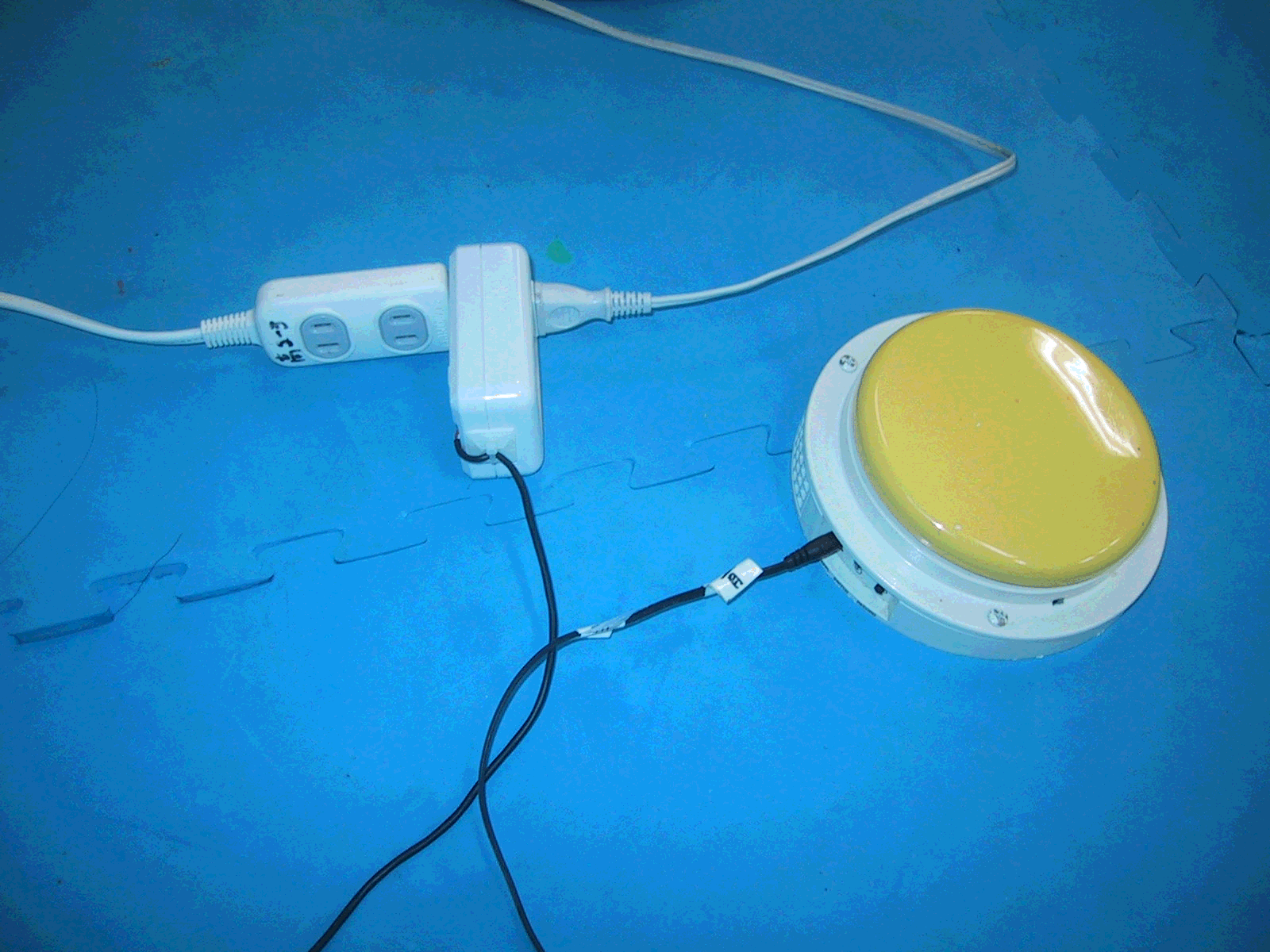 |
| ☆ Let's try!! ☆ 使い方 |
 |
|
☆おもちゃの電車のタイヤに絵の具をつけ、接続すると・・・ |
|
| ☆ こんな子どもに・・・ |  |
| ・ 健康増進を図りたい。 腹式呼吸で矢を飛ばすので呼吸力を鍛えます。 |
|
| ☆ 使い方 | |
| 1 的に向かって集中し、おなかに空気を吸い込 み、一気に吹き出します。 2 筒から「プシュッ!」という音とともに矢が的に 突き刺さります(位置が定まり、集中力の高ま りとともに命中率が上がります)。 注意 まとのまわりには絶対に近づかない。 |
 |
| ☆ Let's try !! ☆ |  |
| 1 筒~塩ビ管 1メートル、直径13mm (競技用はアルミや真鍮を用います。) 2 矢~競技用のものを使用する。 (呼吸が弱い場合は安全ピンの先をセロテー プで留める。) 3 的~25cm四方の用紙に円(黒・赤・黒)を 描く。1辺が30cm、厚さ5cmの発泡スチロ ールに張り付ける(的が外れることを考慮し て大判の発泡スチロールを使用してもよい)。 ◎ 簡単にできますので、ぜひお試しください。 |
| ☆ こんな子どもに・・・ | 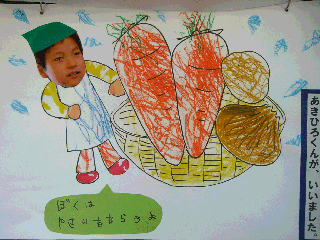 |
| ・ 身近なものの名称やひらがなの読み 書きの力をつけたい。 |
|
| ☆ 実態差が大きい学習集団では | |
| みんなで一つのものを作り上げ、発表することで達成感を味わうことにもつながります。 | |
| ■絵グループ | □文字グループ |
 |
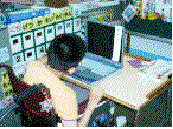 |
| ・ひらがな並べ、拾い読み ・ものの名称 ・実物に合うものの色ぬり |
・単語カードを並べ、ストーリーを作る。 ・場面にあうせりふを考える。 ・文章やせりふを書く(手書き、パソコン) |
| ☆ Let's try !! ☆ | |
| 児童生徒にとって身近な話題を題材に、児童生徒の言葉を取り入れながらストーリーを作ってみましょう。色ぬりや友達・教師の写真など、楽しい活動や素材を準備することがポイントです。 | |
| ☆ こんな子どもに・・・ | |
| まひ等による手指の動きの不自由さから、細い鉛筆をにぎることが困難な児童生徒に。 個人の手の形に合わせた補助具をつけることで、筆記用具が持ちやすく、書きやすくなります。 |
|
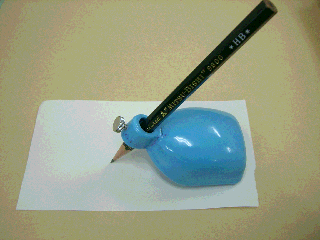 |
☆ ほかに・・・ |
| 「ペンホルダー」という市販品もあります。マウスのような形になっていて、ホルダーに鉛筆を固定し鉛筆の芯の先を紙面に密着させて、コンピュータのマウスのように、転がすように操作すると自由に描画や書写ができます。 | |
| ☆ ねらい |  |
|
| ・自分のボディーイメージをもつこと ・空間と自分との関係を位置づけること ・見たり、聞いたり、触ったりする感覚を養ったりそれらの感覚を組み合わせて使ったりすること |
||
| ☆ 作り方と使い方 | ||
| <準備物> 透明シート(2M×1.5M)、網(張り替えようの網戸)、ひも、フラフープ、送風機、 ビニール袋、お花紙、透明テープ <使い方> ①透明シートを筒状(円柱状)にします。 ②下に三角すいになるようにビニール袋をつけ、頂点を切り、送風機の口を入れます。また、一カ所穴をあけ、お花紙を入れる場所を作ります。 ③天井部分は、フラフープに細かい網などをつけ、風が通るようにし、ひもをつけてつるします。 ④変形防止のため、筒の中央部分にもフラフープをつけ、お花紙を入れ、送風機で風を送るとお花紙が舞います。紙などを口に入れてしまう子供がいても大丈夫。 |
||
| ☆ さらに・・・ | ||
| お花紙の色を変えたり、風の量を変えたりすることで舞う様子が変わってきれいです。スポンジなどの軽い素材のものも風の力で舞い、とても楽しいですよ。 自分の視覚、聴覚、触覚などを上手に使えるように様々な感触遊び、空間を使ったダイナミックな活動を友達と一緒に楽しみながら行ってみましょう。 |
||
| ☆ Let's try !! ☆ | ||
 |
 |
 |
| <新聞紙すだれ> 下を歩いたり、キャスターボードに乗って通ったりします。顔や体に触れ、感触を楽しめます。引っ張って切ったり、揺らしたりして遊んだりもできます。 |
||
| ☆ ねらい | |
| 注意を促し、自発的な働きを引き出します。 | |
| ☆ Let's try !! ☆ | |
| <準備物> ろくろ、円形の板(画用紙がおける位の大きさ)、模造紙、ガムテープ、四つ切り画用紙、 セロテープ、ポスターカラー、液状洗濯のり <使い方> ①ろくろを用意します。 ②円形の板に模造紙を曲線に沿って折りたたみ、ガムテープでとめます。 ③上に画用紙を載せて裏側の四隅をセロテープで固定します。 ④ポスターカラーと液状洗濯のりを混ぜ合わせて準備し、生徒が選んだ色を画用紙の上に垂らします。 ⑤ろくろを回して、手を置くと瞬時に色が変形し、こどもは不思議な感覚を体験できます。 <始める前に・・・> 割烹着や古いワイシャツ、エプロン等を着用して汚れを防ぎましょう。 |
 |
| ☆ ねらい | |
| ボールを動かしたり動かす様子を見せたりすることで注意を促し、自発的な動きを引き出します。 | |
| ☆ Let's try !! ☆ | |
| <作り方> ①画板を置き、下に画板より大きく段ボールを切り取り、周囲に段ボールや厚紙で立ち上がりを作ってガムテープで止めます。 ②裏にテニスボールをテープで貼り付けて簡単に傾くようにします。 ③前面の画板の上に画用紙を置き、ポスターカラーを付けたスポンジボールやビー玉、ピンポン玉等を置き、前後左右に揺り動かすとボールの動きで簡単に線画ができます。また、墨汁を使うとインパクトの強い線画ができ、色画用紙を使うと雰囲気の違った作品ができます。画板の代わりに箱型段ボールにガムテープを敷き詰めると色がふき取りやすいです。 <始める前に・・・> 割烹着や古いワイシャツ、エプロン等を着用して汚れを防ぎましょう。 |
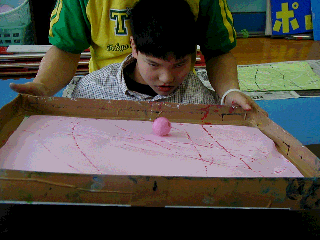 |
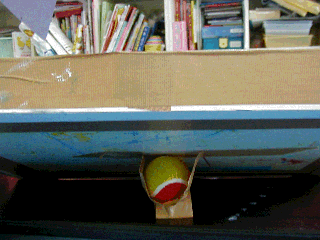 |
|
| ☆ こんな使い方も・・・ | |
| 墨汁を使うとインパクトの強い線画ができ、色画用紙を使うと雰囲気の違った作品ができます。画板の代わりに箱型段ボールにガムテープなどの絵の具が浸透しない素材を貼り付けると、絵の具がふき取りやすく、使用後の始末も楽にできます。 | |
10.机
| 日常的に使用する物を児童生徒の身体の状態に合わせて整えていくことは、大変重要なことです。中でも、書字や制作活動、食事などの際に使用する机の選択は、適切な学習環境を整えることの大切な一つです。 | |
|
☆周囲に落下防止用の枠をつけた机 |
 |
| ☆腹部の部分や電動車いすのコントローラー部分をくり抜いた机 車いすが入るように机上面が一般の机より広くなっています。個人の車いすの形状に合わせてくり抜き、より使いやすいものにしています。 |
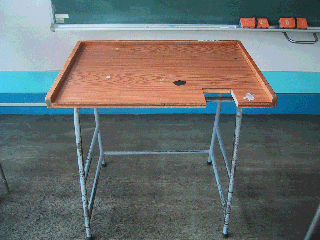 |
|
☆膝立ちの姿勢で使用する机 下肢の緊張が強い場合、下肢を固定することによって上肢のコントロールをスムーズにするために作った手作りの机もあります。(使用児童の家族が作製したもの) |
 |
|
☆ こんな使い方も・・☆  |
|
11.いす 
|
☆背もたれ、肘置きのあるいす |
 |
|
☆身体に合わせて作製したいす |
 |
|
*座位保持具 |
 |
12.歩行器
| 児童生徒の心身機能の維持・向上のために、校内の授業等で使用している歩行器についてご紹介します。 | |
|
☆PCウォーカー |
 |
|
☆SRCウォーカー(Spontaneous Reaction Control walker) SRCウォーカーは、前傾姿勢で身体を保持するサポートを備えた歩行器です。支持面が4面で広く、安定性が高いもので、サイズはS・M・L・LLがあります。 |
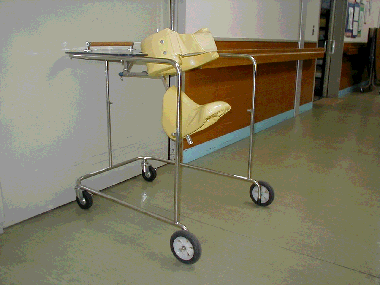 SRCウオーカーサドルあり  SRCウオーカーサドルなし |
| ☆ Let’s
try !! 歩行練習という課題だけではなく、車いすで自操が困難な児童生徒も、これを使用することによって好きな所へ自由に移動することが可能になる場合があり、心身の解放もねらうことができます。また、日々の継続によって、体力面の向上、生き生きとした表情やのびのびとした動きを引き出すことに効果的な場合もあります。 |
|
|
☆ねらい |
|
| ☆作り方と使い方
腕に引っかけてひもを引っ張ると、留め金がはずれ、ゴムパチンコの原理でボールを飛ばすことができます。受け皿には即席カップ麺の空容器を使用します。ゴムの強弱でボールの飛ぶ距離を調節できます。 |
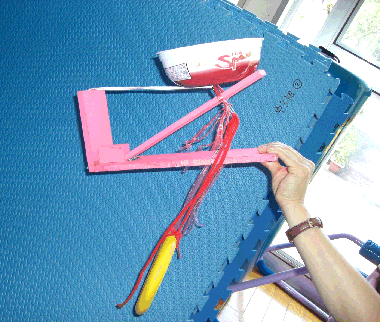 |
| ☆こんなふうに使っています!
運動会では、「玉入れ」の競技に活用しました。受け皿にテニスボールを入れてひもを引っ張ります。前方のかごに見事入りました! |
 |
| ☆ Let's try !! 引っ張るひもの端に輪投げの輪や使用済みの粘着テープの輪を用いると、握りやすいでしょう。テニスボールだけでなく、水風船などを入れて風船割りも楽しむことができ、体育以外の授業での活用も考えられます。 |
 |
| ☆ねらい ボールを押す(転がす)力が弱く、なかなか命中させることが難しい児童生徒に。 |
|
| ☆作り方 ボールを乗せるための直方体(または円柱でもよい)の垂木と、土台となる円形(方形でもよい)の板、蝶番を右図のように組み立てます。蝶番の反対側から押すなどして力を加えるとボールが倒れる仕組みです。 |
 |
 |
☆工 夫 1 段ボールとベニヤ板でスロープを作り、 テーブルの上からボールを転がすことで勢 いがつく。 2 大型スロープを使用する際は、ボール が左右に飛び出ないように、マットの両側 に垂木をガムテープで固定する 3 ボールが後ろに反れたときのためにピ ンの後方に、発泡スチロールで覆った卓 球のついたてを置く。 |
| 「ゴロゴロ~」「パカ~ン」という音とともに、押す→転がる→倒れるという一連のボールの動きを目で追う(追視)ことで、集中力を高めることにもつながります。 | |
| ☆ねらい 様々な姿勢や動きの体験を通して、感覚・運動機能の発達と活性化をねらっています。ダイナミックに活動しましょう。 |
|
| ☆キャスターボード +キャスターボード 大型のものがあればベストですが、1M四方のキャスターボードを2枚つなげ、クッション(ブーメラン型が良いです)を固定すればできあがりです。 |
 |
| ☆キャスターボード+大型そり・ゴムボート | |
 |
 |
| ☆工 夫 1 360度回転するキャスターを使用すると自由自在に動きます。 タイヤはゴム製のものが騒音もなく適しています。 |
|
| ☆キャスターボード+ おもちゃ(木馬など) ☆工 夫 2 キャスターボードと他の遊具を組み 合わせることで、様々なタイプの乗り物 への応用ができます。 |
 |
| ☆ねらい 鉛筆やシャープペンシル等をつかんだり、筆圧をかけたりすることが困難な児童生徒が、市販の筆記用具を使って文字を書くことができるように。 |
|
| ☆作り方と使い方 クリップに筆記用具を固定し、輪に人差し指と親指を入れて固定します。特製の樹脂で一人一人の手の型に合わせて作成されています。 (隣接の施設のOTが作成しています) |
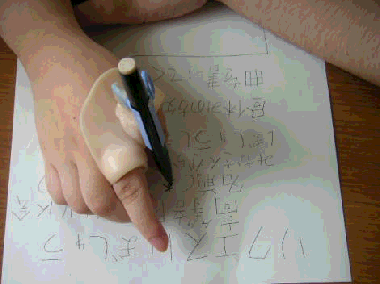 |
| ☆ねらい 食事の際に箸を使用して食べることが困難な児童生徒が、自分で食事をとることができるように。 |
|
| ☆作り方と使い方 通常のフォークやスプーンを対象児の手の使い方に合わせた角度に曲げます。取っ手の部分を太くすることで、弱い力でも持ちやすくなります。フォークは、食物を刺して口まで運ぶことができます。 |
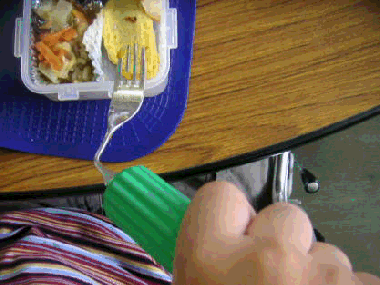 |
| ☆ Let's try !! 食事の補助具として様々なものが市販されていますが、高価なものです。市販の一般的なスプーンやフォーク、先割れスプーンなどで代用すれば、安価に、そして一人一人により合ったものを簡単に作成することができます。 |
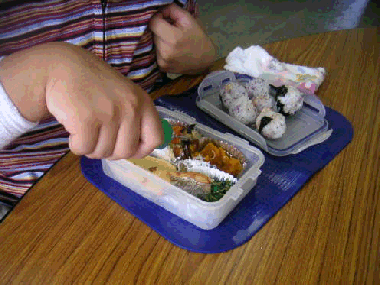 |
| ☆ねらい 普段車いすを使用している児童生徒が、車いすとは異なる地面から伝わる振動を感じながら風を切って走ることで、手軽に雪国のスキーを楽しみ、爽快感を味わうことができます。経験を広げることにもつながります。 |
|
| ☆作り方と使い方 スキーとパイプいすをレールにビスで固定します。姿勢を保持しやすいように手すりや足台を付けています。雪上で使用しますが、自作のキャスターボードに取り付けると、屋内でも使用することができます。 |
|
| ☆ Let's try !! こんな使い方も・・・ ○クリスマスの季節には、ソリの周りを装飾し て、「トナカイのソリ」にもなります。 ○県立スケート場の受付に話しをすれば、スケ ートリンクでの使用も可能です。 |
|
| ☆ねらい 児童の可能な身体の動きを利用して楽器を鳴らすことができるようにします。意欲の喚起や音の違いを感じ取ること、自分でできたという達成感を味わったりすることをねらいます。 |
|
| ☆作り方 1 鍵盤より幅の狭い板を必要なだけ用意しま す。 2 板の端に布などを巻きつけてふくらみをもた せる。 3 キーボードの鍵盤に板を両面テープ等で、は ずれないように固定する。 |
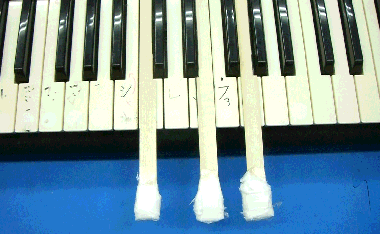 |
 |
☆ポイント ○鍵盤をのばすことで、手が届きやす くなります。また、腕やひじを支持す ることで自ら手首や指を動かして鍵 盤にふれることができます。 ○鳴らしてほしい音だけを選択して提 示することができます(和音で設定 すると音の響きがきれいに聞こえま す)。 |
| ☆ Let's try !! 音や色の弁別をねらって、布に色をつけて提示する、板の長さを児童の身体の状態に合わせて調節するなどの工夫をしてみましょう。 |
|
| ☆ねらい バチを握ることが難しい場合でも、児童の可能な身体の動きを利用して楽器を鳴らすことができるようにします。意欲の喚起や自分でできたという達成感を味わったりすることをねらいます。 |
||
| ☆材料 板(5cm×40cm位のもの)、タオルハンガー(挟み付き)、テグス、凧糸、カードリング、ヒートン2本(5mm位のもの)、持ち手用のひも ☆作り方 ①板の端にタオルハンガーを挟んで固定し、上 記の部品を組み合わせる。 ②大太鼓に固定する。 *組み立て方の詳細は、本校にお問い合わせ下 さい。 |
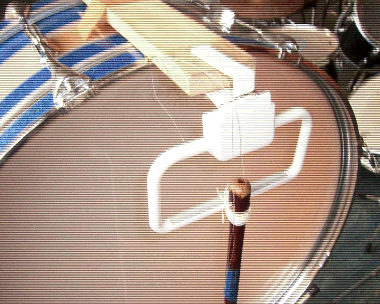 |
|
 |
☆ポイント
○身近な材料で、安価に作成できます。 |
|
| ☆ Let's try !! 取り付ける楽器は、大太鼓だけでなく、鈴やハンドベル等、他の楽器にも応用することが考えられます。持ち手の材質や形、硬さなど、使用する児童生徒に応じて工夫してみましょう。 |
||
|
☆ねらい
|
 イルミネーションの部屋 イルミネーションの部屋 |
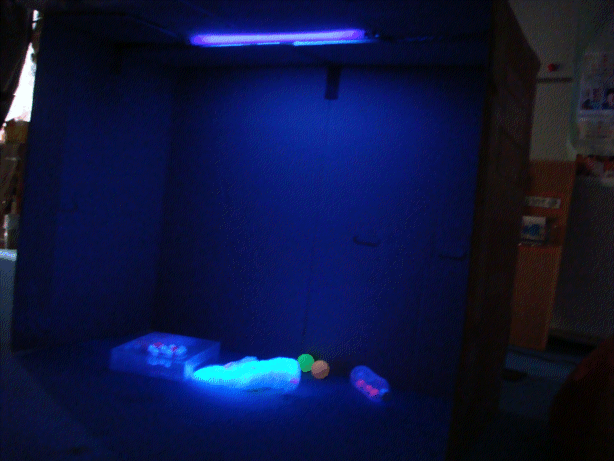 ブラックライトの部屋 |
材い料~ 丈夫で大きい段ボール(冷蔵庫や洗濯機等)、ガムテープ、クリスマス等のイルミネーション(※スイッチで光り方が変わるとなお良いです) 作り方~ 段ボールで左のような部屋を作ります。(屋根も丈夫に作りましょう)段ボールの天井や壁にキリで穴をあけて、イルミネーションの電球が出るようにします。外側の線、コードをガムテープで固定して完成です。 |
| ポイント・・・壁や天井に光があるので、追視や注視しやすく手を伸ばすことができます。また、寝ながらでも光を見ることができます。 ・光と同時に音楽を流すことにより、視覚、聴覚を総合的に活用できるようになります。 ・AAC等のスイッチ教材を組み合わせることで、より個々の児童の実態に合わせた教材に発展します。 |
 スタンドライトの部屋 |